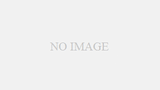こんにちは
アラフォー看護師で
一児の母である
ダイエットサポーターのmakiです♪
先日、
我が家に『あかちゃん訪問』が来ました。
市区町村によって、
訪問時期や名称が異なりますが、
国の『新生児訪問』や
『乳児家庭全戸訪問事業
(こんにちは赤ちゃん事業)』等の政策により
日本で産まれた赤ちゃんのおうちすべてを
訪問する事業があるのです。
今日はそんな「赤ちゃん訪問」を受けてみて
実際の様子や受けてみた感想などを紹介していきます。
新生児訪問と赤ちゃん訪問とは?違いは?
新生児訪問に赤ちゃん訪問・・・
日本で赤ちゃんの産まれた家庭を訪問し
支援する制度は二つ名称があるようです。
とはいえ、その違いはなんでしょうか?
簡単に紹介します。
新生児訪問とは?訪問時期は?
新生児訪問は、正式名称を『新生児訪問指導』と呼びます。
母子保健法第11条によって
定められた事業で、
助産師や保健師が、
赤ちゃん宅を訪問する保険サービスです。
訪問時期は生後28日以内となっていますが、
里帰りなど
赤ちゃんやご家庭の状況で、
60日以内となることもあるそうです。
訪問を受けるにあたり費用は0円!
無料で相談できるのは嬉しいですね。
赤ちゃん訪問とは?
赤ちゃん訪問は、
乳児家庭全戸訪問事業
(こんにちは赤ちゃん事業)で、
児童福祉法第6条に定められたものに
なります。
訪問期間は生後4ヶ月以内となっており、
助産師や保健師、看護師、
保育士、母子保健推進員、
子育て経験者などが訪問する
保健サービスです。
訪問の名称は自治体によって異なるようです。
こちらも費用は0円です!
二つの事業をまとめると、どちらも、
生後半年と経たない赤ちゃん宅を訪問し、
赤ちゃんの発育や発達状況の確認
生育環境
ママやパパの心身の健康状態、
そして、受けられるサービスの紹介をしてくれるものです。
違いとしては、管轄となる法律の違いだけのような気がします。
赤ちゃん訪問を受けるための手続きは?
新生児訪問・赤ちゃん訪問はそれぞれ、自治体によって名称や訪問時期が違います。
また、訪問を受けるまでの手続きや
通知の仕方も違うようなので、
ここでは私の住まいエリア(東京郊外)の
ケースを紹介します。
まず、赤ちゃんが生まれたところで
夫に『出生届』と一、緒に
『出生連絡カード』を
市役所に提出してもらいました。
※出生届の提出は生後14日以内なので
私は1週間の入院が必要だったので、
手続き関係は夫にお任せしました。
『出生連絡カード』の提出により、
赤ちゃん訪問の担当部署に
出生の連絡が行くようです。
提出から2週間ほどしてから、
地域の保健福祉センターから電話が来ました。
その時に、赤ちゃん訪問の日程を決めます。
また、赤ちゃん訪問の際に準備しておくものも
お知らせがありました。
赤ちゃん訪問の際、準備しておくもの
・バスタオル1枚(赤ちゃんの体重を測るのに敷くもの)
・おむつ2枚(体重を測るときに重さを計る用と交換用)
・母子手帳
(訪問時、妊娠から出産までの経過をみたり、
訪問について記載してくれます)
・母親の身分証明書
私の住まいエリアの場合、
赤ちゃん訪問は生後28日以内の早い時期で
行っているようでしたが、
私の場合、里帰りをしていたので、
生後2か月過ぎたごろになりました。
それでも問題なく来てもらえました!
赤ちゃん訪問を受けると10万円分のポイントギフトがもらえる!?
赤ちゃん訪問を受けるメリットは
育児不安を軽減してくれるだけでは
ありません!
私の住むエリアでは
赤ちゃん訪問を受けることで、
子育て支援として、もらえる
10万円分のギフトカードを受け取るための
申し込みをその場でできるのです。
この10万円分のギフトカードは
元々東京都の『赤ちゃんファースト』の
事業の延長で、
都内でも住むエリアによって申請方法が異なるようです。
私の住まいの場合は
赤ちゃん訪問を受けることで
受け取れるようでした。
赤ちゃん訪問の時に、保健師さんが持ってきた書類と封筒に、受け取り希望のサインと、
ギフト券の送付先の住所の記載をしました。
余談ですが、この、
「住むエリアによって違う」
「申請しないともらえない」
「諸々の申請先が異なる」
産前産後の忙しい時期には特に厄介だと思いませんか!?
申請漏れがないように、
市役所窓口と子供支援の窓口、
所属の健康保険組合それぞれに、
確認するとよいです。
管轄が違うと、窓口の人によって
「知ってる」「知らない」があるので・・・
一つの窓口だけで聞くのは危険ですよ!
赤ちゃん訪問の実際:所要時間は?準備するものは?問診のないようは?
8月の暑い中、社会福祉センターから1人の保健師さんが来てくれました。
訪問の30分前に確認の電話をもらいます。
事前に言われていた、
赤ちゃん訪問時に準備するもの
・バスタオル1枚
(赤ちゃんの体重を測るのに敷くもの)
・おむつ2枚
(体重を測るときに重さを計る用と交換用)
・母子手帳
(訪問時、妊娠から出産までの経過をみたり、
訪問について記載してくれます)
・母親の身分証明書
これらを用意します。
地域柄、車でお越しになったので、
車を停める場所の確保が必要でした。
家に家族・友人意外を招くのは初めてなので
ちょっと緊張していましたが、
笑顔が優しい、
先輩ママさんって感じの方でした。
家に上がるとまず
手洗いをさせてほしいとのことで
洗面所に案内。
洗ったタオルをお渡ししようとしましたが、
ご自分で持ってこられており、
使いませんでした。
赤ちゃんのいる部屋に案内し、
赤ちゃんとあいさつ。
夫も育休中だったので親子3人で面談です。
まず、私の産後の体調を気遣う言葉があり、
今の生活がどうか、赤ちゃんのいる生活に慣れてきたかなど、様子を訊かれました。
私は一番に、授乳のことが心配だったので、
母乳が実際足りているかどうか、
授乳前後の赤ちゃんの体重を計ってもらうこともできました。
授乳前に、赤ちゃんの体の診察。
聴診器で、胸や背中の音を確認。
手際よく、反射の確認もします。
丁度お腹がすく時間帯だったので、
泣かないか心配でしたが、
優しい手に触れられてか、安心した様子で
リラックスモードでした!
授乳している間に、
渡した母子手帳から、妊娠中や出産時の状況を
持参されていた書類に書き写していました。
それから問診。
予防接種の案内と
赤ちゃんと参加できる地域のイベントや施設の情報をもらいます。
産後の仕事復帰についても悩んでいたので、
地域の保育園情報の載った冊子も紹介してもらいました。
そして、一枚の問診票を渡されます。
エジンバラ産後うつ病自己評価票(EPDS)というもので、
母親の心理状態、育児ノイローゼや
産後うつの早期発見に使うような内容でした。
10問ほどの項目に、4段階評価をする形だったのですが、
元々海外で使われているツールのようで、
翻訳・言い回しが一部おかしくて、
こたえずらい内容もありました。
他にも、
経済的な不安はないか
相談できる相手はいるか
夫からDVを受けていないか
(夫を目の前に、ちょっと気まず問いかけでしたが)
一通り答えてから、その場で保健師さんが内容を確認します。
チェック項目で心配になりそうなことを
深堀され、解決の窓口となる
助言をもらいます。
私の場合、保育所を探す方法や、
地域の児童センターなどの情報を
もらいました。
また、利用するかは分かりませんが、
一時保育やファミリーサポートなど
育児サポートに関する情報提供もありました。
盛りだくさんの内容で、訪問からの所要時間は
およそ1時間半ほどでした。
終わりに
出産後、退院してからはじまる
赤ちゃんとの生活がスタートします。
訊いてはいたものの、
夜間関係なく続く、3時間ごとの授乳に
寝不足・・・。
赤ちゃんのいる生活に
幸せを感じながらも、
これまで行っていた家事との両立に
産後の体調不良が重なったりして。
赤ちゃん訪問はそんな
体力的にも精神的にも不安定になっているときの助け船のような感じもします。
家族・友人意外に、
頼れる「だれか」ができるといいですね!
今日もあなたとベビーが
笑顔でありますように☆